上地流創流100周年記念イベント参加レポート
7月26~27日の2日間にわたり、上地流唐手の始まりの地である和歌山にて100周年記念イベントが開催されました。
湘南修武館から参加した方々のイベント参加レポートをご紹介します。
また、湘南各道場にて参加者からの報告会も予定していますので、貴重な体験について是非道場内で共有いただきたいと思います。
本部道場 藤本きよみ 指導員

忘れがたき3日間となった和歌山でした。
上地流創流100周年という節目に上地流が産声をあげたその地に立ち、縁の地を巡り、改めて藤本館長の著書「上地完文風雲録」を読み返しじわじわと自分のいる今を確認しています。
初日、隆聖館友寄道場に向かうタクシーで行き先を告げると上地流が和歌山で産声をあげたこと、友寄道場のことを知っているドライバーで、藤本館長が引き寄せる何かを目の当たりにし、上地流にぐっと手繰り寄せられました。
友寄道場では上地寛文先生、友寄隆優先生が今でも存在するかのような独特の空気が流れており、このふたりの出逢いがなければ、上地流唐手はこの世になく、今の私もいないのだなと実感しました。
100周年記念演武会、祝賀会は参加者全員、またその場にはいなくても上地流唐手の修行をする仲間たちの想いがここにあると感じられる素晴らしい時間となりました。
そして、この隆聖館友寄道場にて行われた特別昇段審査会は本当に特別で
これを書きながら思い返し感謝の涙が溢れ出るほどです。
最後に、和歌山へ行く直前の稽古で、藤本館長が子どもたちに「いいか、間違えるなよ」と諭していたこの言葉、人生は常に様々な選択の積み重ねで成り立っていることを実感しています。
ひとりひとりの選択の積み重ねでこの100周年を迎えられたこと、関わっているみなさまに感謝の念が尽きません。
本部道場 落合敏宏 会員
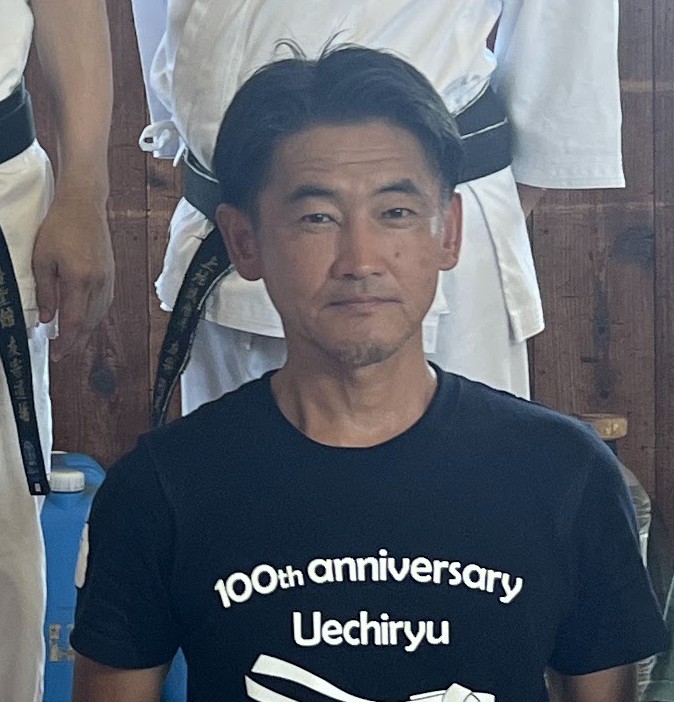
仕事を終えて藤本館長が執筆された「上地完文風雲録」を機内で読み返しながら和歌山へ向かった為、どこか現実から離れた感覚で和歌山の会場に到着致しました。
一人の小さな子供を福建省に残し、やむを得ず帰国され和歌山市手平で友寄先生との出会いからパンガイヌーン流が始まり
そして百年が経ち、上地流の修練をする可愛らしい子供達や、穏やかな心と鍛えられた体を備えた素晴らしい人格者を数多く世界中に創られた功績を、この百周年記念演武会で拝見させて頂きました。
上地完文先生が創流された唐手道を修練されて来た方々の演武は歴史の重みがあり、道場ごと型の違いがありましたが、半硬軟が基本にあり繋がっていると感じる物が御座いました。
そして生涯に渡る心身の健康と人間形成の道が得られる可能性のある武道武術であるとあらためて理解致しました。
感動を覚える素晴らしいイベントでした。先生方に心より感謝申し上げます。
鎌倉道場 吉田信一 師範

上地流唐手道100周年イベントに参加して
まず、今回、このイベントに参加表明したのは今年の2月でしたが、その後、仕事の都合で栃木県への転勤となり大きく生活環境が変わりこのイベント直前までどうなることかという日々を過ごしてましたが、なんとか無事参加することができました。
上地流唐手の修行の中で、今まで、沖縄訪問、また完文先生が晩年過ごされた伊江島にも訪問する事ができ、そして今回いよいよ和歌山手平の地を訪問する事ができ大変感慨深い思いです。
初日の演武会では3団体が同じ型や鍛えなどを披露しましたが、3団体それぞれ解釈が違いとても新鮮であり貴重な体験でした。長年に渡り、解釈や伝わり方が道場により変わって来た事であり、どれも正解であるという事だと思います。
最終日は、隆聖館友寄道場で短い時間でしたが三戦を学び、灼熱の中、皆で手平の町を散策し完文先生が当時過ごしていた情景が手に取るように感じられました。
今回、上地流創流100周年という貴重な節目に和歌山の地で迎えられた事は唐手人生に於いて何よりの宝です。
今後も更に精進して参ります。
鎌倉道場 山梨卓馬 会員

今回、100周年記念イベントにて上地流発祥の地和歌山で演武及び稽古をするという念願が叶い、数日たった今でも感慨に耽っております。
演武会では三戦鍛え及び、上地流の源流である南派少林拳と対になる形で北派の少林拳を演武させていただき大変光栄でした。
二日目の和歌山隆聖館での稽古で隆聖館式の三戦を体験させていただいた際には、その内容の奥深さに感嘆するとともに「やはり三戦の立ち方から見直す必要がある」と大いに勉強させていただきました。
演武会後の宴席でも、関東修武会の仲間や和歌山隆聖館、巴会の方々とも交流を深めることができ大変有意義な時間を過ごすことができました。
今回の経験を今後の修行の糧にして更なる修練に励んで参ります。
茅ヶ崎道場 杉本孝宏 師範
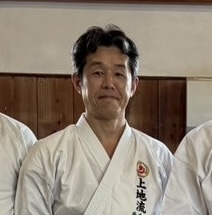
創流100周年の記念イベントにご協力いただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。
このような意義深い場に参加できたこと、大変光栄に思います。
100年前、助け合いや地域のつながりが生活に欠かせなかった時代背景の中、上地流という一つの流派が誕生しました。
もし友寄隆優先生と上地完文先生が出会っていなければ、私たちの流派は存在しなかったことを改めて実感しました。
そしてその後、関西から沖縄、さらには世界中へと広がる中で、お二人の出会いのような巡り合わせが、さまざまな場所で生まれていったのだと思います。
そこには、上地流唐手の魅力だけでなく、それを共に学びたいと思わせる人の魅力もあったことでしょう。
次の100年に向けて、私たち一人ひとりが魅力ある人間に成長し、人と人との巡り合わせを大事にしていきたいと思います。
そして、私たちの上地流唐手の技術・精神・歴史を後世に伝えていきたいと思います。
最後に、今回の100周年イベントの企画者であり、私にとって最も大切な巡り合わせの一人である藤本先生に、深く感謝申し上げます。
茅ヶ崎道場 杉本潤子 師範

創流100周年記念行事に参加させていただき、心より感謝申し上げます。
上地流発祥の隆聖館友寄道場をはじめとする各地の道場が集まり、それぞれの歩みと特色が演武という形で交わる場に立ち会えたことは、大変貴重な経験となりました。
演武を通して、同じ源でありながら、積み重ねられてきた道の違いを知る機会ともなり、心に残りました。
また、創始の地を巡る中で、先人の想いや努力を身近に感じ、自身の歩みを見つめ直す時間ともなりました。
最終日には、歴史ある道場にて審査を受けさせていただき、大変身の引き締まる思いでした。
この節目の行事に関わらせていただけたことに感謝し、今後もこの学びを大切に精進してまいります。
茅ヶ崎道場 加藤崇 指導員

100周年記念演武会では、一人の流祖から始まった上地流が、時を越えて人や土地によって多様に進化してきた姿に触れ、その変化の面白さを実感しました。
記念稽古とゆかりの地の散策では、流祖がこの地で唐手を始めた当時に思いを馳せ、歴史を大切に受け継いできた先人たちへの感謝の念が自然と湧きました。
短い時間ながら、その地で汗を流し、特別昇段審査を受けさせていただけた経験は、今後の唐手修行においても大変有意義なものとなりました。
審査では反省点も多くありましたが、それもまた流祖から「まだまだだな。もっと頑張れよ」と励まされたように感じています。
このような貴重な機会を与えてくださった先生方に、心より感謝申し上げます。
岡山道場 高田昌宏 指導員

上地流100周年記念イベントに出席し、発祥の地を訪ねる機会に恵まれたことに、心より感謝申し上げます。
戦前は手平地区の紡績工場に多くの沖縄出身者が就職されていたことを知り、同じ繊維業に携わる者として深い共感を覚えました。私の実家は祖父の代から縫製工場を営んでいますが、九州や四国から集団就職で多くの女性達が住み込みで働いていた幼少期の原風景と重ねながら、上地流の先達が弟子達と共に活気溢れる手平地区で稽古に励んでいた様子に思いを馳せました。
道場に掲げられた写真を拝見し、また、記念稽古を通じて、上地流空手が積み重ねてきた歴史とその精神が、時を超えて脈々と受け継がれていることを実感すると共に、入門していなければ知り合えなかった皆様との懇親を深める中で、空手を通じた絆の尊さを改めて感じることができました。
100周年の重みを感じながら、次の世代にも繋いでいけるよう、初心に帰って稽古に励みたいと思います。
茅ヶ崎道場 崎廣里愛子 会員

この度は上地流創流100周年記念に参加させていただきありがとうございました。
この貴重な機会を通して、改めて上地流の始まりを知り学ぶことができました。
和歌山手平の紡績時代に、沖縄県人をめぐるつながりの中で運命の出会いがあり、上地流の始まりに隆優先生の存在は大きく、この出会いがなければ現在の上地流は存在しなかったのだということを深く感じました。
ゆかりの地を散策できたことも、とても意義深かったです。ゆかりのエピソードからも、完文先生の生活や人柄を思い描くことができ、身近に感じることができました。
力強く時代を生きながら、人と繋がり、受け繋いできた、歴史の先の先で現代の私達に繋がっているのだ、と実感すると共に伝承とは尊いことなのだ、と感銘を受けました。
和歌山隆聖館友寄道場の建てられた場所について、隆兄館長のお話が印象深く、研究所跡地から道場を拝見してみると、実に聖地を敬いそこに在るような佇まいに心に響くものがありました。
友寄道場で稽古させていただき、源流となるものを肌で感じながら知ることができ、私の中に唐手道における底のようなものがつくられたように覚えました。
和歌山手平の地で心に感じたものを携えながら、これからの修行に励んでいきたいと思います。
茅ヶ崎道場 白井沙幸 会員

和歌山遠征を通して実感した自分の成長は、多くの方の演武を拝見しながら、何故この部分は我々と異なっているのか、どのような鍛錬の末に現在の形式に至ったのか等、各会派が継承してきた教えや技の意味に対して僅かだが考察できるようになっていた事だ。
だが同時に、有段者としての自分の未熟さを痛感した。
記念稽古で友寄道場のサンチンをご教授いただいた際、下野尻先生に最もご指摘を受けたのは「重心の甘さ」。これは関東修武会にとっても大事な要素のはずなのに、全く身についていない事をハッキリと自覚した。
正直メチャクチャ悔しかった。
他にも初歩的な段階での課題は山積みで、持ち帰って結果に表れるまで見直そうと肝に銘じた。
ただ、これらを炙り出せた事自体が大きな収穫だし、なによりものすごく楽しかった。今までとはまた違った意識で“自分なりの上地流唐手道”を歩み、慢心せずに鍛錬の楽しさを追求し続けたいと思えた最高の2日間だった。
茅ヶ崎道場 今井尚信 会員

前日の和歌浦湾に吹く海風と穏やかな空気とは一転して、初めて訪れた友寄道場には、 喧騒の中にもただならぬ気配が漂っていました。
それは、65年間にわたり修行者たちが流してた血と汗の積み重ねによるものなのか、あるいは建物そのものが醸し出す風格によるものなのか一言葉では言い表せない空気がそこにはありました。
実は、藤本館長から上地流の和歌山イベントの構想を初めて伺った際、正直なところ、自分にに縁遠いもののように感じていました。
しかし、思い切って参加してみると、自分が実は多くの人々の交差と積み重ねの一端に触れていたのだという思いが湧き上がり、最終的には「感謝」という、ありふれていながらも深い一言に尽きる気持ちとなりました。
そして、100年という歳月に対して、「いつまでもあると思うなよ」と語りかけられたような気がしました。
人生の折り返しを過ぎた今、数多くの先生方や先輩方には到底及ばないと感じながらも、 もしも許されるのであれば、厚かましくも上地流の一端に在り続けたいという思いを強くしています。
今回の企画を立ち上げてくださった先生方に、心より御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
茅ヶ崎道場 野中香織 会員

100周年記念イベントは非常に内容が充実していて、忘れられない二日間となりました。演武会では、同じ上地流でも型や三戦に違いがあることを実際に見て感じることができ、構え方や間の取り方の違いがとても興味深かったです。今日の稽古で体験もさせていただきましたが、やはり湘南修武館のやり方が体に染みついており、真似ることすら難しいと実感しました。
友寄道場では、一歩足を踏み入れただけで背筋が伸びる思いでした。長い歴史の中で多くの方々が鍛練してきた空気を肌で感じ、100年の歴史に加わらせていたいたことを嬉しく思うと同時に、このご縁を今後も大切にしていきたいと思いました。
今回、貴重な機会をいただき本当にありがとうございました。
茅ヶ崎道場 吉川美沙月 会員

上地流唐手道100周年イベントに参加し、多くの学びや驚きを得ました。私がこのイベントに参加した目的は、「上地流唐手とはどういう意味が込められて作られたのか」、「流派の歴史」などを知りたいと考えたからです。
上地流唐手は、約100年前から現在まで流派の特徴である三戦の型、小手鍛え、足先を使った技など、ほぼ原型を維持しながら受け継がれてきた点に強い感銘を受けました。
イベントでは多数道場の演武を拝見でき、同じものでも少し違った物を見ることができました。特に「どうしてその技を行うのか」という理由まで丁寧に解説されており、とても興味深かったです。
上地流が現代まで継承されてきた歴史に対し、“流派を守る責任”や“重み”を実感しました。
祝賀会では他道場の方々と直接会話する機会があり、練習方法や技術に関する情報交換を通して、交流の場として非常に有意義で大切な時間となりました。
平塚道場 山本創 師範
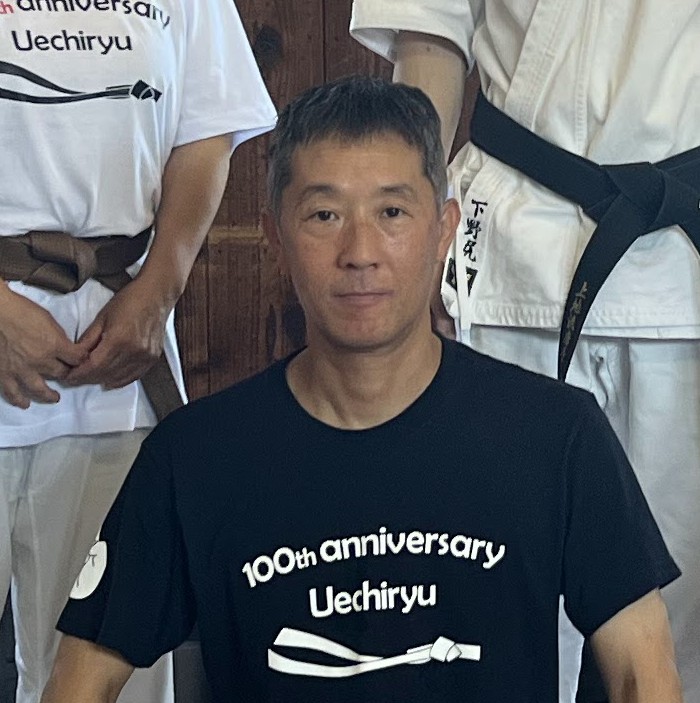
今回の和歌山遠征は私にとって非常に有意義な3日間となりました。100年前の和歌山の地における上地完文先生と友寄隆優先生の出会い、そして上地流唐手を継承されてきた先生方に感謝の気持ちを抱きながら身の引き締まる思いで濃密な時間を過ごすことができました。
さて、今回、和歌山隆盛館、巴会塚口道場の技法を改めて拝見し、その違い、特に貫手の狙い処、受け技の使い方、掴みや三戦鍛えの考え方の違い等が印象的で100年前の教えを今なお忠実に継承されているのであろうことに感銘を受けました。
一方で、長い歴史の中で少しずつ技法を変革させていった結果が修武会のものなのかもしれませんが、100年前の原点と我々の今を見比べることは非常に興味深いものでした。
最後に、この和歌山の地、歴史ある隆盛館の道場で昇段審査の機会をいただけたことに心より感謝いたします。
魂の燃え盛るような気持ちでいられたのは一生の思い出です。
ありがとうございました。
平塚道場 佐々木祐一 指導員

友寄道場、巴会、関東修武会により演武会を行いましたが改めて基本の流れに部分的な違いを学びました。
翌日、友寄道場にて記念稽古を行いましたが、まず、下野尻指導員による三戦指導に自分の実力の無さに気付かされました。
①三戦の立ち方(足幅が広め)
②足の運び(運び足が床より離れる)
③突きの手が胸元で止まる
④突きが水月目掛けて下目に就く
⑤突く手が薬指と小指を曲げている(就く際二本指が折れないようにするため)
三戦の鍛えで水月の突きで部員殆どが後ろに押されてしまうという結果でした。立ち方の基本を指導授けましたが足裏の親指と人差し指の種子骨の間で立ち、更に足裏で床を掴むこと。
三戦の鍛えで水月の突きで部員殆どが後ろに押されてしまうという結果でした。
立ち方の基本を指導授けましたが足裏の親指と人差し指の種子骨の間で立ち、更に足裏で床を掴むこと。
記念稽古後ゆかりの散策では、上地完文師と沖縄出身の友寄隆優師との出会いにより手平町に道場を構えることとなった街並みを散策しました。
沖縄県民のための長屋が今でも残っています。
今回参加して、稽古(古を考える)を行っていなかったことを反省する記念研修でした。
平塚道場 岸圭介 会員

この度友寄道場、塚口道場の皆様と周年祭という場で互いの交流、流祖ゆかりの地散策などをしました。
伝承系譜の異なるこのニ道場の演武を見た際、同じ三戦でも修武会の三戦とは大きく異なるものでした。
それぞれの挙動で重視している箇所が異なっているのです(例えば友寄道場では貫手で狙う位置が結構低い、など)。
しかし、元を辿れば同じ先生から教わっているのですから、どれも全て正しいのだと思います。
むしろ差異こそが残す必要のあるものなのかもしれないと感じました。
なぜなら各道場の始祖は完文先生からの教えで、大事だと思うものを弟子に伝承していると思うからです。
その上で二道場の型を見ると、なるほど、こういうことも完文先生は教えてたんだな、と新たな視点を得ることができました。
今回は貴重な機会を与えていただき、ありがとうございました。